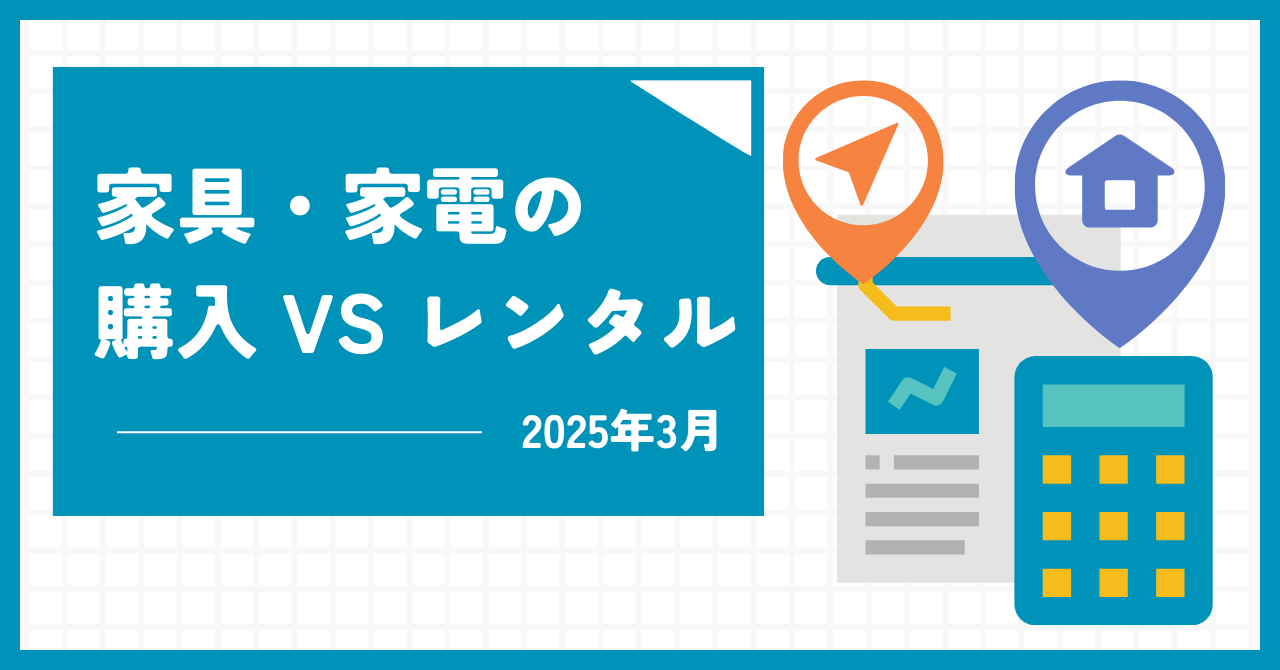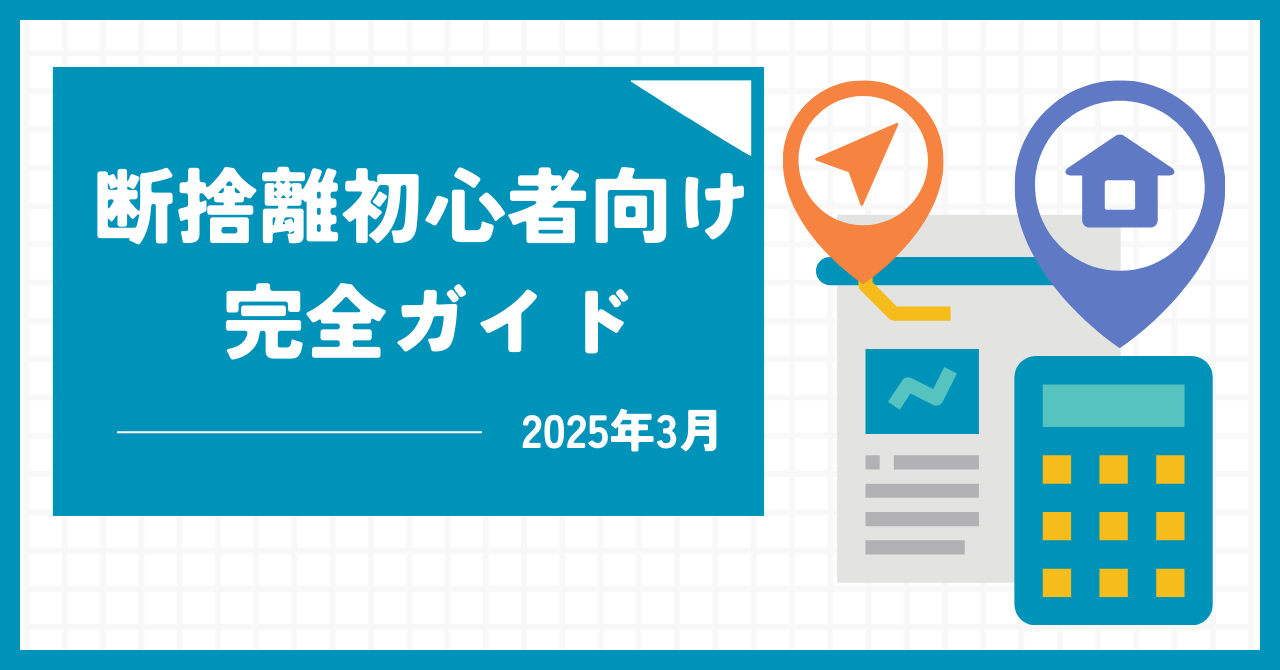こんにちは、なくまるです!
引越しの際、意外と気になるのが「退去費用」。
敷金はちゃんと戻ってくるのか、高額な修繕費を請求されないか、不安になる人も多いですよね。
実は、退去時の費用には「借主が負担すべきもの」と「大家さんが負担するもの」のルールがあります。
これを知らない人は、本来支払わなくてよいお金まで請求されることも…。
この記事では、敷金が戻るケースや適正な修繕費の基準についてわかりやすく解説!
ぜひ最後まで読んでみてください!
退去費用の基本
敷金とは?
賃貸契約時、大家さんに預けるお金のことです。
このお金は、賃借人が家賃を滞納した場合や、退去時に部屋を元の状態に戻すための原状回復費に充てられます。
一般的には、入居者の故意・過失による傷や破損の修繕に利用されるので、キレイに入居していれば返金されるケースが多いです。
原状回復とは?
原状回復とは、賃貸を退去する際に、入居時の状態に戻すこと指します。
これは、借主が使用中に発生した汚れや傷を修繕し、元の状態に戻すことが求められるという意味です。
例えば、壁に穴が空いてしまった場合や、床に傷が付いた場合なども含まれます。
特に、ペットによる床や壁の傷は、借主が注意していれば避けられる損傷として見られることが多いので、ペットを飼っている場合はその点に気をつける必要があります。
適正な修繕費とは?
「適正な修繕費」とは、賃貸時の契約に基づいて借主が退去するべき修繕費用のうち、実際に発生した損傷や汚れに対して適切な金額であることと考えます。
経年劣化と自然損傷
住宅には時間が経つことで自然な摩耗や劣化があります。
例えば、フローリングの軽い傷や壁紙の日焼け、カーペットの色あせなどは、借主の使用によるものではなく、経年劣化に該当するため、修繕費として請求されることはありません。
また、「通常の使用」の範囲内で生じたキズや劣化についても、基本的に入居者が修繕費用を負担する必要はありません。
- 家具の設置による床やカーペットの凹み
- 壁に画鋲を刺した穴
- エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡
借主負担になるケース
借主が負担すべき修繕費用や原状回復には、主に次のようなケースが挙げられます。
- タバコのヤニ汚れ
- 故意や不注意による損傷
- ペットによる損傷
タバコを吸ったことによる壁や天井のヤニ汚れや臭いは、借主が原因となる汚れとみなされ、退去時にクリーニングや修繕が必要になります。
また、お香などの香りが残る場合も修繕費が発生することがあります。
さらに、借主が家具を引きずったり、物を落としたりして生じた傷や破損も、借主の責任として修理費用が発生します。
特に、壁や床に大きな傷がつき、臭いが残る場合は、その修繕に費用が請求される場合があります。
オーナー負担になるケース
一方、オーナー(貸主)が負担すべき修繕費用や原状回復には、以下の場合があります。
- 設備の劣化
- 自然損耗
設備(エアコン、給湯器、トイレなど)の寿命や経年劣化による不具合は、オーナーの負担となります。
同様に、エアコンが古くなって故障したり、給湯器やキッチンの設備が使えなくなったりした場合、これらの修理費はオーナーが負担するべきです。
これらは、物件の経年による自然な損と見なされるため、借主の責任ではありません。
また、壁紙の日焼けやフローリングの軽い傷なども、時間の経過とともに自然に発生する「自然損失」として、借主が負担することはありません。
退去時の費用を抑えるコツ
- 原状回復の範囲を理解する
- 普段から丁寧に使う
- 清掃をしっかりと行う
- 退去前に物件の掃除をする
- 入居の際に傷のチェックをする
賃貸契約書に記載された原状回復の内容を確認し、自己負担となる項目を把握することが大切です。
傷を防ぐためには、床にジョイントマットやフロアタイルを敷き、直接家具を置かないようにするのが効果的です。
また、普段からこまめに清掃を行い、特に水回りや汚れがつきやすい場所を掃除することも重要です。
それから、入居時に最初にある傷の写真を残しておくこと、そして退去時にはしっかりと清掃をしてから出ることを徹底的にしましょう。
まとめ
退去費用トラブルを防ぐためには、賃貸契約書に記載されている原状回復の範囲をしっかり確認しておくことが重要です。
また、退去時にはしっかりと清掃を行い、部屋を綺麗な状態で退出することも大切です。
これらの準備と心掛けが、敷金が戻るケースや適切な修繕費を確保するための鍵となります。
退去費用が高額になる場合は、国土交通省のガイドラインをチェックしてみましょう。